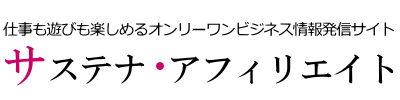近年、InstagramやTwitterなどのSNSを通じて急速に広がりを見せている「新型MLM(マルチレベルマーケティング)」。「簡単に稼げる」「自由なライフスタイルを手に入れられる」というキャッチーな謳い文句で、特に若い世代を中心に参加者が増加しています。しかし、その仕組みや実態は本当に合法なのでしょうか?それとも従来のねずみ講の形を変えただけなのでしょうか?
金融庁や消費者庁も警戒を強める中、新型MLMとねずみ講の境界線はどこにあるのか、その違いを正確に理解することは、不測の事態を避けるために非常に重要です。本記事では、SNSで拡散している新型MLMの実態と、法的にアウトとされるねずみ講との決定的な違いについて、専門家の見解を交えながら徹底解説します。
投資と詐欺の狭間で揺れる新型MLM。その真実を知ることで、あなたやあなたの大切な人が騙されることを防ぎましょう。
1. SNSで急増中!新型MLMの仕組みとねずみ講との決定的な違いを徹底解説
InstagramやTwitterなどのSNSを見ていると、「権利収入が得られる」「在宅で月収100万円」といった投稿を目にすることが増えました。このような投稿の多くは、MLM(マルチレベルマーケティング)と呼ばれるビジネスモデルによるものです。特に最近は、SNSを活用した新型MLMが急速に拡大しています。しかし、これらのビジネスモデルは違法なねずみ講と混同されることも少なくありません。
MLMとは、Multi-Level Marketingの略で、日本では連鎖販売取引と呼ばれています。参加者が商品やサービスを販売するだけでなく、新たな販売員を勧誘することで収入を得られる仕組みです。一方、ねずみ講は、商品やサービスの提供がなく、単に加入者を増やすことで上位者に利益が還元される仕組みであり、法律で禁止されています。
新型MLMの特徴は、実際の商品やサービス(化粧品、健康食品、投資教材など)が存在し、それらの販売による利益が発生する点です。正規のMLMでは、消費者庁に特定商取引法に基づく連鎖販売取引として届出を行い、法的に認められたビジネスモデルとして運営されています。アムウェイやニュースキンなどの大手企業は、この形態で数十年にわたり事業を継続しています。
一方、ねずみ講の場合、商品やサービスは形式的なものか、まったく存在せず、新規参加者の資金が直接上位者に流れる仕組みになっています。このような構造は持続不可能であり、必ず破綻するため、無限連鎖講防止法によって禁止されています。
判断の難しい点は、一見MLMのように見えて実質的にはねずみ講に近い「グレーゾーン」の存在です。例えば、形だけの高額な情報商材を販売し、実質的には会員獲得報酬が主な収入源となっているケースなどが該当します。消費者庁や警察も、こうしたグレーゾーンのビジネスに対して監視を強めています。
正規のMLMに参加する場合でも、十分な情報収集と冷静な判断が必要です。「簡単に儲かる」「必ず成功する」といった甘い言葉に惑わされず、ビジネスの実態や収益構造を理解した上で参加を検討することが重要です。また、家族や友人を安易に勧誘することで人間関係が損なわれるリスクも考慮すべきでしょう。
2. 【警告】投資か詐欺か?SNSで勧誘される新型MLMビジネスの真実とリスク
SNSを開けば「月収100万円達成!」「スマホ一つで不労所得」といった投稿を目にする機会が増えています。特にInstagramやTwitterでは華やかなライフスタイルの写真と共に、「誰でも簡単に稼げる」と謳う投稿が拡散されています。これらの多くは新型MLM(マルチレベルマーケティング)への勧誘です。
新型MLMの特徴は、従来の健康食品や化粧品販売とは異なり、暗号資産(仮想通貨)や海外FX、不動産投資など金融商品と組み合わせている点です。「システムに登録するだけ」「自動で増える」といった謳い文句も特徴的です。
消費者庁によれば、このような新型MLMの相談件数は年々増加傾向にあり、被害総額も拡大しています。金融庁も無登録での金融商品取引に関する注意喚起を行っています。
新型MLMのリスクとして最も深刻なのは、実態がねずみ講である可能性です。ねずみ講とは、商品やサービスの実体がなく、後から参加する人からの会費が収入源となる仕組みであり、日本では無限連鎖講防止法で禁止されています。
見分け方として以下の点に注意しましょう:
・実体のある商品やサービスが存在しない
・勧誘や人集めに大きな報酬がつく
・ビジネスモデルの説明が抽象的で不明確
・「必ず儲かる」「リスクなし」と断言する
・登録料や初期費用が高額である
また、海外サーバーを利用したり、法人登記を海外に置いたりすることで日本の法規制を回避しようとする手口も見られます。金融商品取引法や無限連鎖講防止法の適用を逃れようとするこれらの手法は、詐欺的な要素が強いと言えるでしょう。
弁護士の中には「新型MLMの多くは、実質的にねずみ講であるケースが多い」と指摘する声もあります。国民生活センターへの相談事例では、友人や知人から誘われて参加したものの、結局は多額の損失を被ったという被害報告が増加しています。
SNSで華やかに見える成功者の多くは、すでにピラミッドの上位に位置しているか、豪華な生活を演出しているだけという可能性も高いでしょう。簡単に稼げるという甘い言葉には十分な警戒が必要です。
3. 金融庁も注目!若者を狙うSNS発の新型MLM、ねずみ講との法的境界線とは
金融庁が警戒を強めているSNS上で拡散する新型MLM(マルチレベルマーケティング)。InstagramやTikTokを通じて「権利収入」「不労所得」といった甘い言葉で若者を勧誘するケースが急増しています。
法律の観点からみると、MLMとねずみ講の違いは明確です。連鎖販売取引(MLM)は特定商取引法で規制される合法ビジネスですが、物やサービスの実体がなく、参加者集めだけで報酬が得られる「無限連鎖講(ねずみ講)」は連鎖販売防止法で禁止されています。
新型MLMの特徴は、商品やサービスが存在するように見せかけつつ、実質的な価値が乏しいデジタルコンテンツを扱うケースが多いこと。例えば、数万円で購入した「投資教材」や「ビジネスノウハウ」が実際には無料で手に入る情報だったというトラブルが相次いでいます。
国民生活センターへの相談件数も増加傾向にあり、「友人からのSNS勧誘で契約したが儲からない」「高額な入会金を支払ったが約束された収入が得られない」といった被害報告が目立ちます。
弁護士の間では「デジタル商材を扱う新型MLMは、法の抜け穴を利用している」との指摘も。消費者庁は「実体のある商品・サービスが適正な価格で取引されているか」「参加者集めが主な収入源になっていないか」が判断基準だとしています。
被害に遭わないためには、「すぐに儲かる」「簡単に不労所得が得られる」といった誘い文句には警戒し、契約前に消費生活センターへの相談を検討することが賢明です。また、日本直接販売協会(JDSA)に加盟している企業かどうかも一つの判断材料になるでしょう。